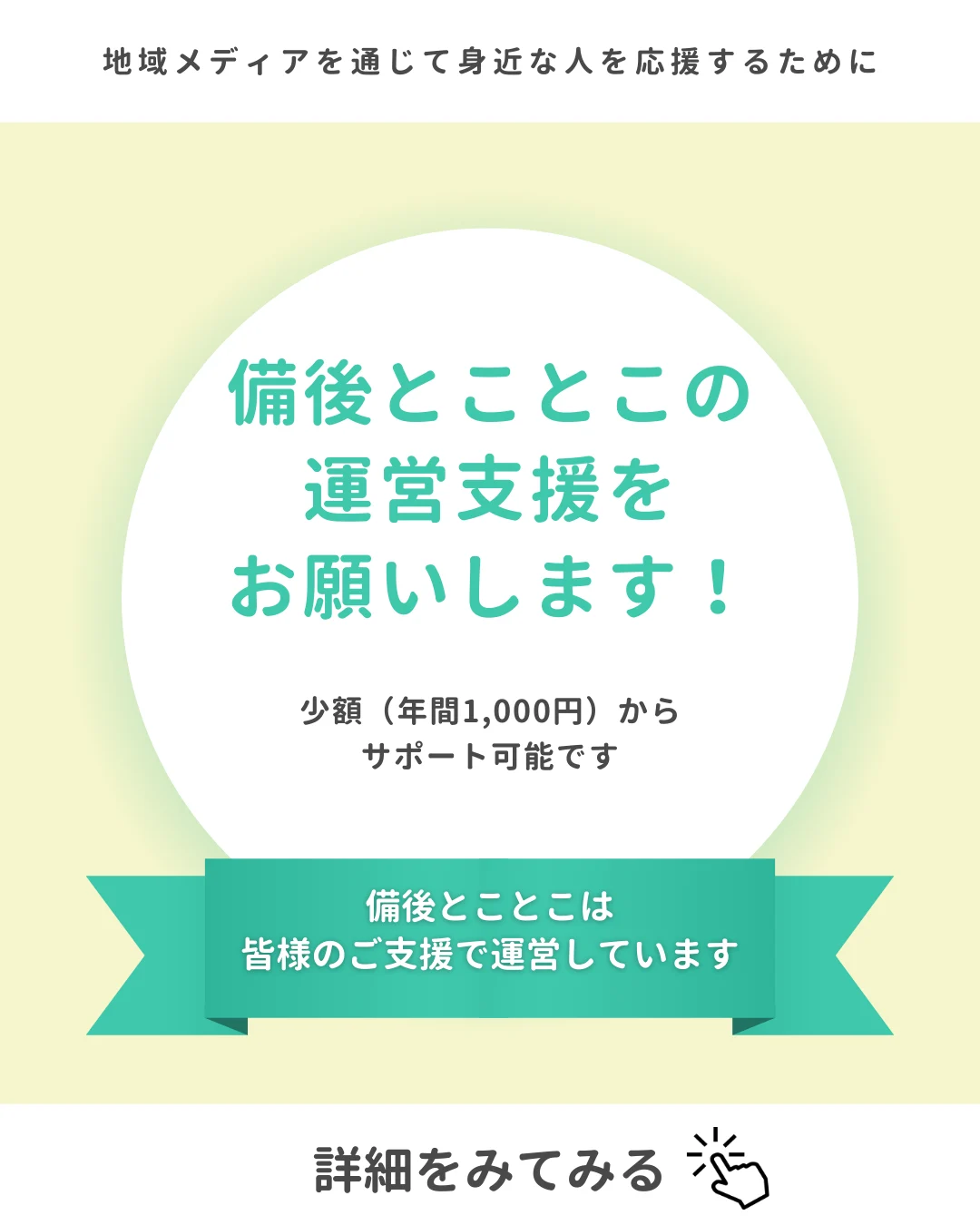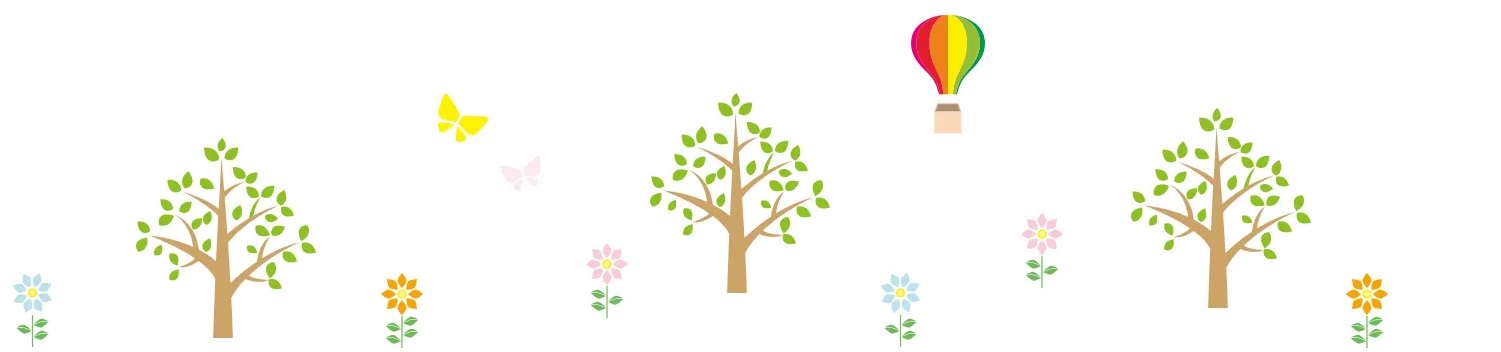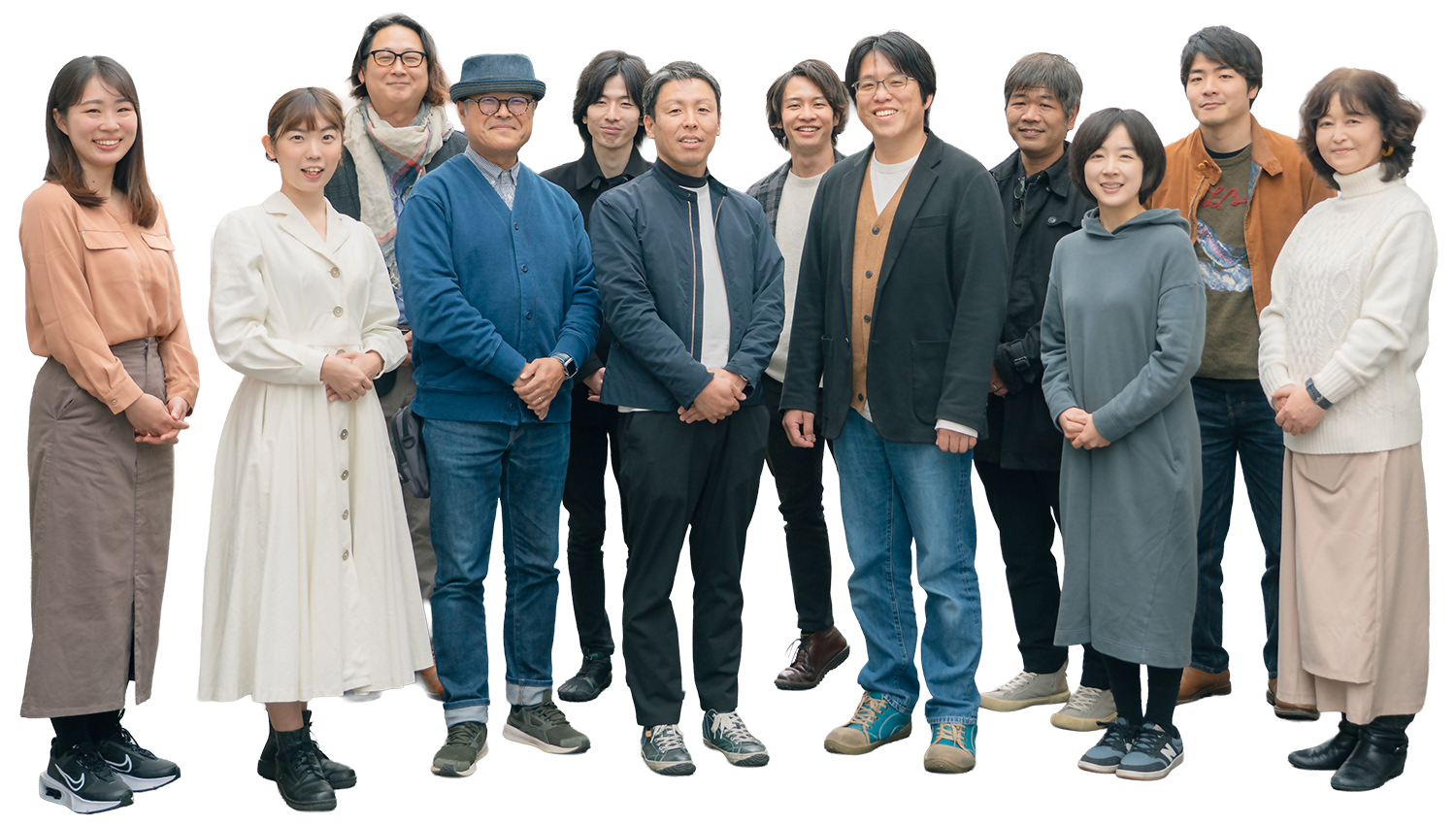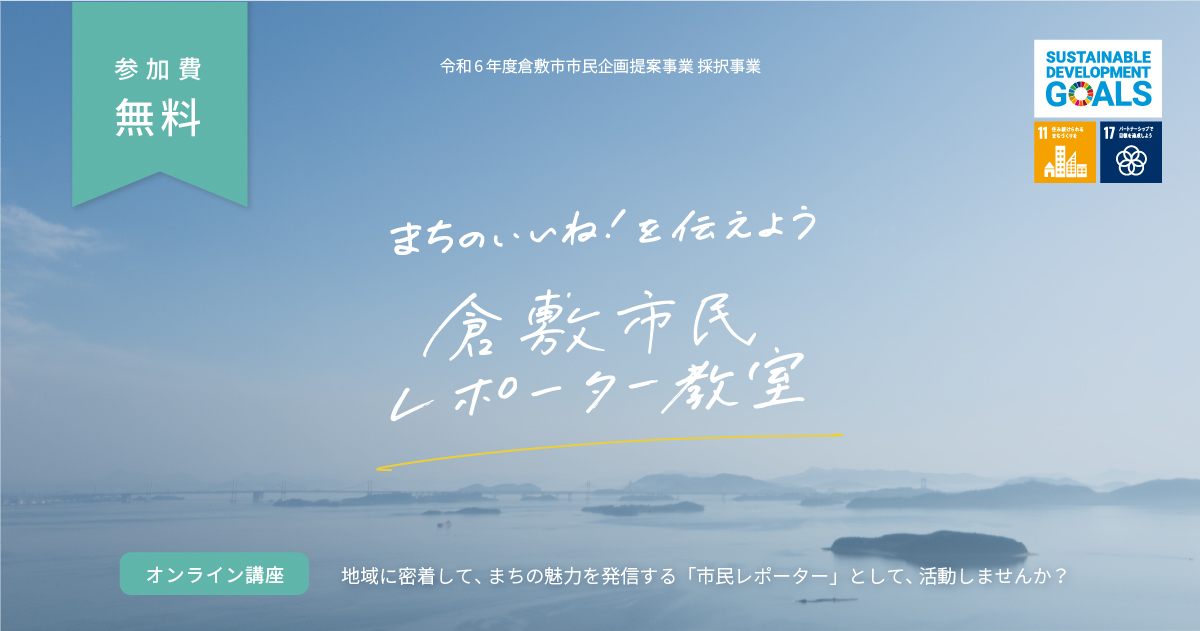「油断していると、簡単に有害な存在になってしまう」
講座の冒頭で、社会では「もの言うマジョリティ」とされる中高年男性(講師自身、筆者も)の言動について、警句として語られたことばです。
当の中高年男性にとって、そうしたことに感づき、配慮しつつも、やはり耳の痛い発言ではないでしょうか。
しかし映画を観ることは、こり固まった既存の意識をアップデートする良い機会になると言います。
劇中でマイノリティの人たちがどう描かれているか、社会はどう変わっていけるのかということに注意を払い、有害な男性性を発揮しないよう、自己をかえりみることのできる格好のケーススタディになりうるのです。
ただそれらの作品のなかには多様性を描いた先進的な表現ゆえに、読み解きの難しいものもあるため、本講座は多くの人に望まれるイベントだったのでしょう。
過日、福山駅前シネマモードで開かれた、まちゼミ講座「映画と多様性」についてレポートします。

記載されている内容は、2025年4月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
Ads by Yahoo! JAPAN
目次
まちゼミ福山 シネマモード講座「映画と多様性」
2025年3月29日(10時30分~12時)、福山駅前シネマモード カフェスペース AREA INN FUSHIMICHO(エリア・イン・フシミチョウ)カフェラウンジで、講座「映画と多様性」が開かれました。
本講座は福山商工会議所主催「第23回 まちゼミ福山」の一環で開催されたトーク・イベントで、映画検定1級を所有し、同館ティーチインなどでも度々登壇している、福山駅前シネマモード ディレクター岩本一貴(いわもと かずき)さんが講師をつとめます。
講座のサブタイトルは「ジェンダー、性的マイノリティ、人種・民族的マイノリティ、障がい者などを映画はどう描いてきたか。あなたをアップデート&エンパワーメントする映画たち」というもの。これは映画制作は近年、多様性を対象としながら、新たな表現を模索していることを示唆するテーマです。
簡易スクリーンが設けられたカフェの一隅には、二十数名の参加者がつめかけ、これまでに公開された映画において、多様性はどのように描かれてきたのか、またそれらの表現に関連して考えておきたい「感動ポルノ」や「当事者キャスティング」といったトピックについて耳をかたむけていました。

映画業界の多様性受容の流れ
岩本さんはまず、社会の動きと連動して、映画業界が多様性をどのように受け容れていったかに着目します。
「社会に多様性が必要だということは随分と議論されていますが、映画業界で多様性が芸術性を高めるものと言われ始めたのはごく近年のことです。そうしたことが言われ始める以前のところまで、簡単に振り返ってみたいと思います」
ここでは時流にならって、当時SNSで盛んに流布された『3つの#(ハッシュタグ)』を手がかりに考察していました。

黒人の人権を主張する強い求心力
一つ目は、#BlackLivesMatter(ハッシュタグ ブラック・ライヴズ・マター)です。
黒人の怒りの声がSNS上で拡散されてアメリカ各地の暴動をあおり、野火のように広まったBLM(Black Lives Matter)のニュースは当時、日本にも生々しく伝えられていました。
詳細を岩本さんが語ります。
「2012年、フロリダ州で黒人の少年が、自警団の白人男性(ラテン系との混血:ヒスパニック)に射殺されるという事件が発生。正当防衛を主張したこの男性が無罪判決を受けたことに対し、2013年にSNS上で、#BlackLivesMatter、つまり黒人の命も大切というハッシュタグが拡散されたんですね。
ブラック・ライヴズ・マター以降に公開された映画では、2013年、黒人奴隷を描いた『それでも夜は明ける』、2016年、黒人の同性愛者を描いた『ムーンライト』、2018年、1960年代を舞台に黒人差別を描いた『グリーンブック』などがあり、黒人を主人公にした重要な作品が多数つくられました。
グリーンブックは1960年代を舞台にしていますが、黒人を取り巻く環境は変わらないままではないかということを突きつけるために、あえてこの年につくられたのではないでしょうか」

白人ばかりのオスカー受賞への批判
二つ目が、#OscarsSoWhite(ハッシュタグ オスカー・ソー・ホワイト)。
興行に大きな影響力を持つ権威ある賞が改めて、どのような属性の人が決定権を掌握しているのかという再考を促す動きでした。
岩本さんは続けます。
「アカデミー賞のことを批判的にそう言っているわけですが、同賞は監督や俳優、スタッフなどの映画業界人から構成される会員の投票で決まるんですね。
このハッシュタグが登場したのは2015年で、2015、2016年にはアカデミー賞の演技部門にノミネートされた俳優が男女ともすべて白人だったということが大変物議を醸しまして、#OscarsSoWhite、つまり白すぎるオスカーというハッシュタグが拡散されたと。
そこからアカデミー賞もちょっとまずいなということで、女性や人種・民族的マイノティ、アジアの人も含め、積極的に入会を勧めました。で、会員の多様性を図ることによって、受賞作品も変わってきていると思います。いまでは会員の3分の1が女性で、非白人も増えている(19%前後)ということです。
2019年の韓国映画『パラサイト』、2022年には、アジア系の家族を描いた『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』がアカデミー賞作品賞を受賞したのも、アジア系の会員が増えたということが一つの要因ではないかと個人的に思います」

映画業界を震撼(しんかん)させた内部告発
三つ目がもっとも大きなムーブメントだったと考えられる#MeToo(ハッシュタグ ミー・トゥー)です。
これはまさに業界内部から噴き出した問題でした。
圧倒的な男性優位が生んできた性加害、またその隠ぺいを許すまじという数々のリークが大きなうねりとなって、ハリウッドの一時代を築いた、大物プロデューサーを失脚に追い込む大騒動に発展しました。
岩本さんは話します。
「発端は、2017年10月にニューヨークタイムズ紙が映画プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインが1990年代から数十年にもわたって、社内の女性スタッフや自社作品に出演する女優、若い女優志願者などに性暴力、および性的虐待を繰り返していたと発表したことでした。
しかしなぜ、そこに至るまで発覚しなかったかと言うと、ワインスタインが事件を口外すれば映画界にいられなくなくするなどと脅迫し、一部の被害者に対しては口止め料を払って、守秘義務を含む示談契約を結んでいたからなんです」
ニューヨーク州とロサンゼルスの裁判所に合わせて約40年の禁錮刑を言い渡され、現在服役中のワインスタインは、どのような人物なのでしょう。
「1996年に『イングリッシュ・ペイシェント』、1999年に『恋におちたシェイクスピア』などをプロデュースし、それらの作品がアカデミー賞を受賞しています。自ら「ミラマックス」という会社を経営し、1990年代から2000年代にかけて、同社作品がアカデミー賞受賞、およびノミネートされることが大変多かったんです。
一方でクエンティン・タランティーノと組んで、たくさんの作品を制作していることでも有名でした。つまりアカデミー賞常連プロデューサーとして、業界内で絶大な力を持っていたために、加害行為が構造的に隠ぺいされていたんですね」

#MeTooムーブメントを追い風に映画業界への女性進出は加速し、そうした流れから注目すべき女性クリエイターも頭角をあらわしています。
「#MeTooムーブメント以降は、フェミニズム的な作品が増えたように感じています。たとえば、ワインスタインを告発したニューヨークタイムズ紙の記者を描いた、『シー・セッド その名を暴け』が2022年につくられています。
2023年の『バービー』はマーゴット・ロビーという俳優が制作をして、グレタ・ガーウィグという監督と女性コンビを組むかたちで、世界的な大ヒットに導きました。ジェンダーをテーマにしながら、はじけたユーモアのセンスのあるミュージカルシーンもたくさんあり、かつ深い示唆に富む映画で、これが世界的に受け容れられたのはとても良い兆候だなと感じました。
さらにこのマーゴット・ロビーは、2020年の『プロミシング・ヤング・ウーマン』で、女性の性被害を描いた作品もプロデュースしていまして、今後も彼女の企画力に注目していきたいと思っています」

アカデミー作品賞を席巻する多様化の波
多様化を求める気運が、ついにアカデミー作品賞にも現れるようになったことを岩本さんは次のように考察しました。
「人種マイノリティやLGBTQなどを描いた映画が、アカデミー賞のもっとも高い作品賞を当たり前のように受賞するようになったのは、やはり会員が多様化したことがひとつの大きな要因だと思います」
- 2013年 黒人奴隷を描いた『それでも夜は明ける』が受賞
- 2016年 黒人同性愛者を描いた『ムーンライト』が受賞
- 2018年 黒人差別を描いた『グリーンブック』が受賞
- 2019年 韓国映画『パラサイト』が受賞(アジア映画、アジア系俳優の台頭)
- 2020年 高齢貧困女性が主人公の『ノマドランド』が受賞
- 2021年 ろうあの家族をもつ少女を描いた『コーダ あいのうた』が受賞(ろうあの役をろうあの俳優が演じた)
- 2022年 アメリカに暮らすアジア系家族を描いた『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が受賞
- 2024年 セックスワーカーが主人公の『ANORA アノーラ』が作品賞を含む5部門で受賞
「2013年の『それでも夜は明ける』、2016年の『ムーンライト』、2018年の『グリーンブック』。
それから2019年の『パラサイト』、2020年は高齢貧困女性が主人公の『ノマドランド』。
2021年には、ろうあの家族をもつ少女を描いた『コーダ あいのうた』、この作品のろうあの役はろうあの俳優が演じたことでも話題になりました。
2022年の『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、そして先のアカデミー賞では、2024年に公開された『ANORA アノーラ』が受賞。若きストリップダンサー、アノーラの等身大の生きざまを描き、作品賞を含む5部門で受賞するという快挙はアカデミー賞対策が奏功したかたちです。
いまやアカデミー賞は、一定の多様性を促進するための基準を設けており、作品賞の対象となる映画には、一定の多様性基準を満たすことが求められるようになりました」

多様性を確保する基準が変えていくこと
アカデミー賞の作品賞の対象となる多様性を確保するために設けられた基準があります。同賞のゆくえを方向づけそうでもある基準について、岩本さんは以下のように解説しました。
「作品賞の対象になるためには、4つの基準のうち2つ以上を満たす必要があり、その基準のひとつに、メインキャストの少なくとも1人はアジア系やヒスパニック、黒人、先住民などのマイノリティであるという要件があります。
ただこれはテーマがあまりにも限定されてしまうので、それができない場合は、監督や撮影監督、そのほかのスタッフに女性やLGBTQ、障がい者といったマイノリティを起用することでも基準を満たすことができます。
とにかく映画の内容そのもの、もしくは制作のスタッフが多様性を持っていないと作品賞の対象にならない可能性があることを、アカデミー賞は示しているんですね。
ただそうした取り組みの成果はまだ十分に出てないかなと思うんです。というのが、先日のアカデミー賞の作品賞10作品、監督賞5作品を見ても、ノミネートされた女性監督は『サブ・スタンス』のコラリー・ファルジャ監督ただ1人でした。
それだけ長らく男性社会で回ってきたので、なかなかすぐには反映されないとは思いますけども、徐々に変わっていくのでないかという期待をしています」

多様な視点をすくい上げて芸術性を高める
ハリウッドを中心とする映画業界の、多様性を作品に果敢(かかん)に盛り込もうとする近年の動きは一過性のものではないと、岩本さんはさらに見解を述べます。
「日本国内の映画業界人や映画ファンのなかには、PC(ポリティカル・コレクトネス)だのコンプライアンスだの規制にしばられるのは非常に窮屈(きゅうくつ)で、かつては許された破天荒な表現ができなくなるという人もいるかもしれません。
しかし多様性は映画をせばめ、押さえつけるものではなく、スタッフやキャストが多様化することで、いろんな立場の人の視点が入り、ひいては映画の芸術性を高めるものだと私は思っています。
同時に興行である映画は、その商業性も重視しなければならず、(白人)男性ばかりが主人公の映画ではやはり観客も偏ってしまうので、多様な俳優が出演する、あるいはいろいろなテーマの作品に開いていくほうが、自ずと収益が上がっていくとハリウッドも踏んでいるはずです。
大局的な方向性として、アジア系の人、黒人の人、障がいのある人が主人公になることで、世界各国でさまざまな人種のお客さんが来てくれるような映画をつくろうということでもあるんだろうと思います」

涙を誘う演出として障がい者を消費する「感動ポルノ」
マイノリティが登場する作品のなかには、観客の感情を安易に誘導するような描きかたをするものも見受けられ、当事者などから批判の声が上がることもあります。
「感動ポルノについても考えておきたいですね。語義的には(報道やCM、ドラマ、映画などで)障がいに負けずに頑張る清く正しい障がい者を描き、非障がい者が感動ストーリーとして消費する表現です。
これはオーストラリアのコメディアンであり、骨形成不全症による身体障がい者の当事者でもあるステラ・ヤングさんが2014年のTEDxSydneyでの講演で広めたことばです。
この表現が指摘するのは、その背景にある社会的な問題、たとえばバリアフリーの不備、障がいへの偏見といったものが逆に見えにくくなってしまうこと、また障がい者は純粋で努力家といった固定観念につながることなど、それらは当事者、非当事者のどちらにとっても有害だと思います」
感動ポルノという表現がセンセーショナルだったためか、国内外でさまざまな議論の俎上(そじょう)に上がってきたようです。
「実際にBBC(英国放送協会)は、障がい者を勇敢なヒーローや悲しむべき犠牲者として描くことが差別につながる可能性があるとして、番組制作におけるガイドラインを設けています。
国内でも、トランスジェンダーの人物を主役に据えて、日本アカデミー賞2部門を受賞し、動員的にもヒットした映画『ミッドナイトスワン』に対し、薄命の同性愛者を描いたストーリーは観客の涙を誘うための誘導とも取れ、展開の必然性に疑問を感じるとの批判が一部でありました。
ライターの松岡宗嗣(まつおか そうし)さんは、“本作を見た人の受け取り方はもちろん人によって異なるが、映画を見たうえでこういった批判的な視点についても考えてみてほしい。そして、今後はマジョリティの考えとトランスジェンダー像ではなく、現実に生きるトランスジェンダーのリアルを描く作品が生まれてくることを期待したい”と述べています」

マイノリティのリアルな姿を描く「当事者キャスティング」
安直な感動ポルノに陥ってはならないと言われる一方で、演じ手も多様な当事者であるべきという声も大きさを増しています。
「多様なマイノリティのリアルな姿を描くために、いま試行錯誤されているのが当事者キャスティングですね。障がい者やLGBTQという役柄の登場人物は当事者が演じるべきという考えかたです。
実際に障がい者・LGBTQの登場人物を当事者が演じる作品は増えています。一方で有名な俳優が出演していないと集客が難しいとか、演技力の高い俳優であれば、十分にリアリティが出せるといった意見もあるんです。
ただ過去には、当事者のキャスティングがかなりレアなケースだったわけですけども、現在はキャスト候補として当事者を検討することはめずらしくないと思いますし、友人役などに当事者を起用した作品『ケイコ 目を澄まして』という事例もみられます」

当事者キャスティングを推し進める仕組みづくりも、重要な課題といえそうです。
「俳優にとって経験値はとても重要なものなので、当事者俳優は小さな役から経験を積んで、大きな役にステップアップしていくという道筋が十分に考えられます。
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』にメインキャストとして出演している、当事者俳優の忍足亜希子(おしだり あきこ)さん。彼女が銀行員、手話番組への出演を経て、俳優を志望した理由は“ろう者はもっと明るい。リアルな姿を伝えたい”と思ったからだそうです。
当事者のリアルな姿を描くには、俳優だけでなく制作スタッフにも当事者やそれに近い人が参加することが必要かと思います」
制作費の違いなどから、国内と容易に比較できませんが、欧米ではスピード感をもって対応しているという印象につながる次のような取り組みもあります。
「アメリカでLGBTQをあつかう作品には、LGBTQ+インクルーシブディレクターというスタッフが脚本の段階から参加して、主要キャスティングなどに性的マイノリティに関する指摘や助言をするのだそう。
制作現場にも変化が見られ、実生活でも車椅子を使用する当事者俳優がキャスティングされた映画『ウィキッド ふたりの魔女』では、バリアフリーを細かく整えて、撮影がおこなわれたそうです」
観客であるわれわれも、当事者キャスティングは映画の質を向上するという認識を広く共有していくことが求められているのではないでしょうか。

多様性の現在を知る オススメ映画11選
今回の講座のなかで、講師の岩本さんがセレクトした映画(公開年/監督名)を挙げておきます。
・『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(1975年/シャンタル・アケルマン)
・『テルマ&ルイーズ』(1991年/リドリー・スコット)
・『ハッシュ!』(2002年/橋口亮輔)
・『オアシス』(2002年/イ・チャンドン)
・『ムーンライト』(2016年/バリー・ジェンキンス)
・『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020年/エメラルド・フェネル)
・『隔たる世界の2人』(2020年/トレイヴォン・フリー、マーティン・デズモンド・ロー)
・『マイスモールランド』(2022年/川和田恵真)
・『TAR ター』(2022年/トッド・フィールド)
・『ケイコ 目を澄ませて』(2022年/三宅唱)
・『夜明けのすべて』(2024年/三宅唱)
2010年代半ば以降の作品が中心ですが、それ以前の先見性をもった古いものを再評価する動きも、現在の変化の証しといえそうです。
シネマモードの名画座企画「ヨコゲキ!」
最後に、本稿のテーマ「映画と多様性」について後日、40年前の作品を通じて考える機会を得た、シネマモードの旧作上映&トークイベント「ヨコゲキ!」を紹介します。
RCC(中国放送)のアナウンサーで、俳優や映画監督、映画プロデューサーの経験もある横山雄二(よこやま ゆうじ)さんを迎え、2か月に一度、週末土曜日に開催される人気企画です。
正式名称「天才!ヨコヤマによる名画座企画 ヨコゲキ!」のおとり、国内で公開された膨大な邦画のなかから、横山さん自身がセレクトした作品を上映後、公開時のエピソードやいま注目すべきポイントなどを挙げながら、その不朽(ふきゅう)の名作たる核心に迫ります。
解説パートでは、シネマモードの岩本さんも登壇し、シネフィル(映画愛好家)二人のトークはさらに深く、また意外な関連作品を引き寄せていくのも見逃せません。

この日(4月19日)、第55回のヨコゲキ!では、大林宣彦監督の尾道三部作を締めくくる『さびしんぼう』(1985年公開)をフィルム(非デジタル)で上映。
「多様性と映画」という観点では、大林監督は、性差を超えた人類愛を描こうとした作り手なのではないかといった、興味深い見解を聞くことができました。
おわりに
いまだ男性中心と言われる現実の社会にあって、異性間の理想像を劇的に描いた映画の場面は、空虚な絵空事と受け取られることもままありそうです。
実際に、フェミニズム的な視点から女性主人公を描いたり、シスターフッドと呼ばれる女性同士の連帯を描いたりした作品は増えている印象はあるけれど、恋愛関係ではない男女が連帯するものは少ないと岩本さんは言います。
男女の連帯にあまりリアリティがもてない空気が世にはびこるなか、三宅唱監督の作品はそうした男女間の分断を解消するヒントを描いていて、特に注目しているのだとか。
三宅監督の描く男女の、依存的ではなく見返りを期待しない互助の関係は、日常で見過ごされそうな弱者同士の結びつきの尊さに光を当てようとしているようにも感じられます。
多様性や地域性を織り込んだ映画を上映している福山駅前シネマモードで、作品の優れた視点に触れながら、個人や地域の関心事に思いをめぐらせてみてください。